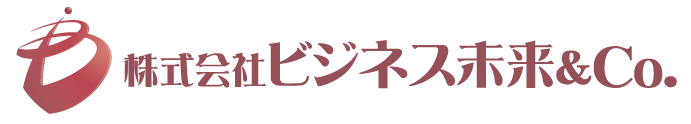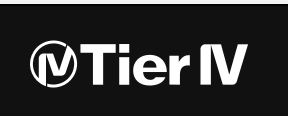事業開発、ビジネスコンサルティング、教育・研修なら “ビジネスみらいアンドコー” へ
コラム 『ビジネス未来』
バックナンバー ④ 2021/7/6 ~ 2021/9/28
タイトル
#049 2021/9/28 トヨタ、水素エンジンで耐久レース完走
#048 2021/9/21 防災について
#047 2021/9/14 自動運転ソフトのスタートアップ
#046 2021/9/7 開業後1年を振り返って
#045 2021/8/31 ゴルフバッグを担いで(2)
#044 2021/8/24 ワクチン接種で大活躍 新潟の中小企業が国難を救えた理由
#043 2021/8/10 米国、2030年の電動車5割
#042 2021/8/3 ダンボール・梱包材の企画・製造・販売
#041 2021/7/27 オリンピックと自粛生活の矛盾
#040 2021/7/20 ゴルフバッグを担いで(1)
#039 2121/7/13 パスワードは、定期的に変更する必要はない?
#038 2021/7/6 車部品、21年度6割増益

ST2クラス優勝のVARIS DXL EVO10
ランエボXらしい!?
トヨタ自動車は、2021年5月22日から23日にかけて、富士スピードウェイに於いて、水素エンジン車で「スーパー耐久シリーズ2021」第三戦24時間レースを完走した。
車両はカローラスポーツを改造して水素エンジンや水素タンクを搭載している。搭載したエンジンは「GRヤリス」の排気量1618ccだ。(水素エンジンで272馬力発生しベースとなるガソリンエンジンと同じ出力)。車両重量は、水素タンクや多くの計測機器搭載により、ベース車両のカローラスポーツより200kg重い。
そしてレース結果は、①周回数が358LAP(走行距離1,634km)、②走行時間は11時間54分と多くの時間をピット作業と水素の充填(4時間5分、35回)に費やした、③水素エンジン車のベストラップは2分4秒だった。ちなみにGRヤリスが参加しているST2クラスの結果は以下の通り。
ST2クラス 第二位 GR YARIS 663LAP
ST2クラス Fastest Lap 1’45”405 (新菱オート VARIS DXL EVO10)
水素エンジンについて、日経クロステック(2021年4月23日掲載記事)ではその特徴を以下のように整理しています。その記事から引用します。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01537/00051/
1.FCV(燃料電池車)に対する利点
(ア) パワートレインとして安価にできる可能性
(イ) 燃料となる水素が安くなる。
(FCV用水素は、純度99.97%に対して水素エンジン用水素は、より低純度の物が利用可能)
2.技術的な課題
(ア) エンジンのバックファイアーの抑制
エンジンの高温部品(吸排気バルブなど)に触れると自着火を起こしてしまう。
(イ) エンジンの冷却損失の低減
水素の燃焼速度がガソリンの7.6倍と非常に速く、燃焼室壁面表層の混合気まで良く燃える。
燃焼室壁面に接する火炎温度が高く、多くの燃焼熱が燃焼室や気筒の壁に逃げてしまう。
(ウ) NOx(窒素酸化物)の抑制
高負荷域では燃焼圧力により、軽負荷域では酸素過多での燃焼温度の高さによるNOxの発生
(エ) 水素を充填する超高圧タンクの開発(これはFCVにも共通する課題)
3. 技術課題解決の目途
(ア) ディーゼルエンジンのような水素噴流火炎の拡散燃焼
水素ガスを予混合しないで筒内に高圧噴射し圧縮自着火させる、あるいは水素ガスを噴射しながら点火する、など燃焼火炎が燃焼室や気筒壁面にできるだけ衝突しないようにする。
(イ)70Mpaの超高圧及び水素脆性に耐える樹脂製のタンクの開発 (豊田合成のHPより)
https://www.toyoda-gosei.co.jp/recruit/rec_graduate/special/story02.html
4. 更に水素インフラの整備
(ア) 安価な水素を大量に生成し、水素ステーションで供給するために水の電気分解以外で水素を得る方法 (電気分解では効率も悪く電気エネルギーが必要となってしまうため。)
(イ) 水素ステーションの建設費(約5億円)と維持費が高い。
とまとめている。
地球温暖化への対応のためにCO2排出量を低減する技術が必要となり、世界的な潮流はEV車だ。しかし、電池原材料の確保や、それとともに生産量の制約など様々な問題が出てくる可能性がある。世界の年間自動車生産量は、生産量上位10か国で凡そ6千万台。これだけでも全数EVに置き換えるための電池原材料は確保が可能なのか?と疑問が残る。そう考えれば、EVに全てを託す一本脚打法よりCO2排出削減のためEV以外のFCVや水素エンジン車など多角的な技術開発が適切だと思う。水素エンジンは従来のガソリンエンジンやディーゼルエンジンの開発及び生産技術が利用でき、一時期流行った直噴ガソリンエンジンの技術など過去の技術的な蓄積も役に立つ。現実的な対応手段だと感じている。
そういえば、英国のジョンソン首相が2030年迄にガソリン及びディーゼルエンジンの販売を禁止(ハイブリッド車も2035年には販売禁止)すると発表している。他の欧州諸国も時期は多少ずれるものの、大筋では同じような内容になっている。温室効果ガス削減の方向性の一つとしては理解するが、全車EV化しかないとする方向性は極端ではないかと思う。やはり政治的な判断なのだろうか。
(U)

週末、台風14号が日本を西から東へ横断していきましたが、皆さんは被害がありませんでしたか?
以前、『#028 2021/4/20 もう始まる?台風シーズン 水温高く上昇気流活発に』で台風について触れたことがありましたが、今回は身の回りの防災について触れてみたいと思います。
先日、9月1日の「防災の日」にちなんで、防災に関するセミナーを受講しました。そこで、私自身、過去から刷り込まれた防災に関する常識や知識が、今や古いものになっていることに気付かされました。
突然ですが、ここで防災に関するクイズです。皆さんはいくつわかりますか?
<クイズ>
第1問:NTTの災害用伝言ダイヤルの番号は171である。 ○? それとも ×?
第2問:大人1人に必要な飲料水は1日3リットルです。 ○? それとも ×?
第3問:南海トラフなど巨大地震に備えて最低一週間分の非常食を用意するのが良い。
○? それとも ×?
第4問:自宅にいる時に大きな揺れがあった場合、避難するならどこが適切?
第5問:洪水で避難する時、道路には水があふれています。履物は、長靴? 運動靴?
<答え&解説>
第1問:〇
第2問:〇
第3問:○
これまで、備蓄は3日分あれば十分と言われていましたが、南海トラフ巨大地震や首都直下地震では、「1週間以上」(2週間必要との見解が有ります)の備蓄が推奨されています。
<参考>
「首都直下地震等による東京の被害想定(平成24年4月東京都防災会議)報告書」
・各種ライフラインの復帰までに要する日数 : 電力7日、上下水道30日、都市ガス60日
第4問:
1981年の新耐震基準適用以降、地震で倒壊よりも怖いのが、家具などの下敷きになってしまうパターン。そのため、以前から大きな家具がないトイレやお風呂は比較的安全な避難場所だと言われていました。(ただし、扉を開けておかないと閉じ込めのリスクがあるので注意が必要。) 一方、玄関も他の部屋より頑丈に作られているケースが多く、扉を開けておけば、いざというときに外に逃げることもできるため、玄関も適切と言われています。
いずれにしても、①倒れる家具等がなく、②閉じ込められないよう扉をあけておくことが、大切です。
第5問:
長靴は中に水が入ると大変重く動きにくくなるうえに脱げやすくなります。運動靴のヒモをしっかり結んで履くことが正解です。
(出典:KOBE防災トータルサイト、ジェイアイ傷害火災保険株式会社「地震の窓口」サイト、内閣府防災情報のページ、地震10秒診断、東京備蓄ナビ)
私の正解数は5問中3問でした。皆さんはいかがでしたか。
さて、今回のセミナーでは以下のサイトの紹介がありました。
1)地震10秒診断 : https://nied-weblabo.bosai.go.jp/10sec-sim/
アクセスする利用者の現在位置において、今後30年以内に震度5弱~震度7までの5段階の揺れに見舞われる確率を表示。その規模の地震が起きた場合に想定される、①停電日数、②ガス停止日数、③断水日数、④家屋の全壊確率(木造及び鉄骨コンクリート造)、⑤出火確率の5種類のシミュレーション結果を提供
2)東京備蓄ナビ : https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/
災害に備えて何をどのくらい備蓄すれば良いか分からない方向けに、備蓄のイロハや備えておくと良い品目などを紹介するサイト。3つの質問に答えるだけで備蓄品目と必要量のリストを表示してくれます。
私も試してみましたが、自分の事として、実感することができました。
<私の居住地の結果>
今後30年以内に震度6強に見舞われる確率:11%
この規模の地震が起きた場合、①停電日数 4日、②ガス停止日数 21日、③断水日数 32日 他
<私の備蓄表示例(食品中心に抜粋)>
水: 42 L、レトルトご飯: 42 食、レトルト食品: 14 個、缶詰(さばの味噌煮、野菜など): 14 缶、栄養補助食品: 14 箱、野菜ジュース: 14 本、チーズ・プロテインバー等: 4 パック、乾麺 即席麺: 7 パック、無洗米: 6 kg、お菓子: 7 パック、果物の缶詰: 7 缶 他
これらのサイトも、是非、一度試してみてください。
最近は、新型コロナ禍の影響で防災イベントが、中止または縮小されています。
「防災の日」に合わせた政府主催の訓練も、昨年に続き感染防止のため関係省庁の関係者を減らしての開催だったそうです。私の住んでいる地区も、毎年2回実施している防災訓練が2年連続で中止されています。このように防災に触れる機会が減っている中、今回のコラムをお読みいただいた皆さん、この機会にあらためて、身の回りの防災チェックをしてみませんか。
(H)
創業者の加藤真平氏が率いるティアフォーは、2015年にオートウエア(自動運転ソフト)を開発し、オープンソースソフトとして公開しました。誰でも使えるオープンソースソフトとして公開してしまうと独占できなくなってしまいます。ティアフォーはこの方法でないと巨人グーグルには勝てない、これならグーグルに勝てると判断しました。既に200社くらいがこのオートウエアを使っているようです。オープンソースソフトなので誰でも使えるため正確にはわからないということです。他にオートウエアの選択肢がないので、大学などの研究機関も含めれば相当な数になるのではないでしょうか。
広げるための発想の転換があります。オートウエアにとってデータをなるべく多く集めてどのような場面でも対応できることが大切と思ってしまいます。ところが、それほどデータは大事ではないと言っています。囲碁のようにオートウエアは“陣取り合戦”になるというのです。例えば日本だけでも地域によって多くの特殊性があります、そこに属する人たちの運転に対する行動様式や運転環境が違います。全てをカバーすることを目指すこと自体に意味があるのかというのです。つまり、東京には東京の、神奈川には神奈川のパラメーターがあるので、利用地に最適化されたオートウエアを考えるということです。東京だけでも処理しきれないくらいのデータは集まるということです。自動運転ソフトは共通、パラメーターは利用目的ごとに運転地域ごとにパラメーターを変えればいいという発想です。お客様は利用エリア、目的、運転嗜好や運転環境に合わせて、自動運転ソフトとパラメーターを自由に選択する時代を目指しているように思えます。分野ごとの“陣取り合戦”です。
【画像出典:TierⅣ社HP】






収益は3本の柱を想定しています。
1)自動運転アプリとパラメーターをお客様の用途に合わせて開発販売
2)上記項目のノウハウをパートナー企業に提供してのロイヤルティ
3)オートウエアのディストリビューター
3項目目はオープンソースソフトであるが故の弱点である事前テスト、不具合対応、そしてサービスをパッケージにして提供することです。リナックスもオープンソースソフトであるためにそのまま商用製品に使う会社はありません。そこには製品保証とアフターサービスをする会社が必要になるということです。
皆で競争しながら良いものを作って、皆で使って価値を一番高くする。このオープンであると競合会社が多くなり、それが巨人と戦う方法だという考え方です。
===============
◆ 小さなベンチャー企業が巨人に勝つ方法
・オープンソースで各社が開発を競う
・開発成果物を共有しその価値を最大化するように各社が取り組む
・必要な人材を広く世界に求めて集める
オープンソースにすることで、巨人にも負けない開発体制を得ることができます。その成果物をどうやって製品化して価値を上げてゆくかは各社の知恵を活用します。そのために必要な人材は世界にいます、元々オープンソースですから。
◆ 今後の展開
ティアフォーは、鴻海精密工業が主導するEV(電気自動車)開発プラットフォーム「MIH」の運営団体に加わりました。これによりMIHでのオートウエアの標準がティアフォーになればMIHで電気自動車を作る人たちが皆使うことになります。インテグレーション、カスタマイズ、メンテナンスまでティアフォーのビジネスは大きく広がります。
===============
ぜひ、自社の業態や製品・サービスに置き換えて考えてみていただければと思います。
(東出)

昨年6月の会社設立から準備期間を経て9月に本格開業してから早いもので1年が経ちました。様々な形で接点を持って頂いた皆さまに御礼を申し上げます。多くの人々がそうであったのと同様に“コロナ、コロナ”の1年であったことは言うまでもないのですが、補助金・助成金を1円も頂けない環境にあった中でも前向きに進んでいくことが出来た方かもしれません。そんな1年目を振り返り、良いこと・悪いこと、そして2年目の展望について今日はお話しようと思います。あまり難しくせず、いくつかの側面から切り取るような形で進めてみます。
■目標の達成状況
初めから大それたことを掲げて活動していけるとは思ってはいなかった1年目です。結果的に
① 会社業績は、想定よりは良かった。(赤字だけど。)
② 営業活動は、コロナ禍による不自由な状態のまま1年が過ぎた。(現在進行形)
③ 今後のサポート案件の開拓や新規ビジネスの創出に時間を使えた。
とまとめることができるでしょうか。
会社は創業時に様々な投資や費用が発生します。設立費用やインフラ整備(事務所やIT機器など)がその主体となり、お仕事をさせて頂くベースとして必要なコストは掛けました。それに対して、“支援の実現機会の創出”がコロナ影響で伸ばせないという当初の想定とは異なる状況になりました。そこは“製造業出身”ですから、コスト低減の方策を自らに実施する形で年度後半の経費を抑制しつつ、お声掛け頂いたお客様の仕事をさせて頂くことで何とか乗り切ることが出来ました。時流ではありますが、リモート化の実践やクラウドサービスの活用は効果が大きかったという実感を持っています。また、在宅勤務により作り出した時間により、Webベースで新たな関係の構築、そして新事業を起こす為の企画などにも時間を使えました。継続性の観点からも2年目以降に繋がる1年目活動になったと総括しています。
■良かったこと・悪かったこと
少し具体的に振り返るべく、『活動面』を良かったこと/悪かったことの形で整理してみます。
【良かったこと】
“ヒト”が資本の企業なので、その面でみると
● 活動メンバーは着実に増やすことが出来た。
● この活動体を面白がってくれた/関心を持って頂けた方々を増やせた。
● 新しいリレーション(人間関係・企業関係)を創り出す機会に恵まれた。
我々のメンバーの多くが“xEV”(電動車)や“リチウムイオン電池”という製品に携わっています。2020年暮れから「脱炭素」の急速な高まりを受けて取組みが活発になったことを受け、経験者・識者が少ない分野ゆえにサポートさせて頂くお話が増えたということがコンサルティング分野では大きかったと思います。この傾向は2年目も続いています。
また、このメンバーの多彩さを活用して製造業以外での新しい取組みを始めています。事業企画分野の取組みとして活動しているものですが、もう少ししたら具体例としてご紹介できるかと思います。
【悪かったこと】
“環境”の側面で見てみると
<外部環境> ひとえに「コロナ」。(もう“語るに及ばず”ですね。)
<内部環境> 取組みの“スピード感”を出しづらい/上げづらい。
やはり外出自粛の中で自宅作業が中心で、思うようなコミュニケーションがFace to Faceで取れないために連携・調整に時間がかかるなど、“新しい日常”は「やりづらさ」に繋がっていました。仕事にテンポやスピード感を産み出し感じさせることがどうしても難しくなりますね。これはお客様にしても然り。「ざっくばらんな意見交換会」や所謂“吞みニケーション”で仕事をしたい方はやっぱり多いと感じています。
良し悪しを特徴であげていくと、こんな風にまとめられる1年だったかと思います。
■では、2年目は
既に入った2年目……というか、ここでは「第二期」とすべきですね。今期は以下の3つのアプローチで活動していこうとしています。基本的には1年目の踏襲ですが、1年目の活動を踏まえて具体像になってきたところもあり、一層の充実を図っていきます。
● 活動メンバー&分野の一層の充実
● 提供サービスのメニューの充実
● 知識・経験・スキルの提供機会の充実
「メンバーの充実」は引続き行なっていきます。来年春に向けて数名増やせれば、と期待しています。当初想定していなかった「管理部門」の分野も“専門性が高い領域”について支援対象に加えることも検討しています。1年目に頂いたご要望の中身から皆さまにとっての“町医者的な存在”を期待されている面があるように感じられ、「まずは話してみよう」という気軽な相談相手となる構えをもう少し広くしておきたいと考えています。
また、「サービスのメニュー」という点では、提供開始が遅れている『教育・セミナー』分野の早期整備を実現したいと思っています。既に「社内研修」については個別・部分的にお受けさせて頂いていますが、会社HPも含めてサービス内容の整備を図っていきます。メンバーとは「研修メニュー」の整備を優先して鋭意作成中です。ネットショップなどを通じたサービス(デジタルコンテンツ/書籍)など、「発信力」の強化もあわせて取り組んでいきたいと思います。
まだまだ駆け出しの会社なので落ち着かないところが多々ありましたが、様々な業界とご縁を結ばせて頂いて様々なご相談を頂けるということも、裏を返せば「知識と経験を移植する多くの機会がある」ということでもあります。企業体力の強化という自助努力も行ないつつ、このコロナ禍でも楽しく・明るく取り組んでいきたいと考えています。
今後ともよろしくお願いします。
(鯨井)


東京オリンピックが閉幕しました。男子は松山プロが銅メダルのプレイオフで敗れ、大変残念でしたが、女子は稲見プロが銀メダルをかけたプレイオフでリディア・コを破りました。改めて、稲見プロの銀メダル獲得をお祝いしたいと思います。
前回の私のコラム(7/20付け)で、米国、英国、英国と3度の海外生活でのゴルフ経験を通した日米英のゴルフ事情について、各国のゴルフ料金とゴルフ場の予約/キャンセルの違いを紹介しました。今回はゴルフコース(含む施設)とプレースタイルについて紹介したいと思います。
◆ゴルフコース(含む施設)について
コースの中で日米英の違いが少ないのはグリーン、次にフェアウェイ、そして最も違いが大きいのがラフだと思います。
最初に、グリーンの傾斜についてです。私の経験では、米>日≧英の順でグリーンの傾斜が強く、極端な例ですが、米国の傾斜はきつくボールが止まらずに、カップを外れたボールは、グリーンの外に転がり出てしまうので、米国人は、このグリーンはイリーガルだ!とよく文句を言っていました。実際に、3,4パットは当たり前で、どうして良いのかわからず困った記憶だけが残っています。
次にフェアウェイとラフは、日・米と英国との違いを大きく感じました。特に英国は季節差が激しく、夏はカチコチでどこまでも転がり続ける感じですが、冬はべちょべちょでランが全然でないどころか、高い弾道だとフェアウェイに埋まることもあり、フェアウェイでロストボールという悲しい経験もしました。特にラフは、フェアウェイより更に柔らかく、シューズだけでなくズボンも靴下も泥だらけになり、毎回、ラウンド後は、家でシューズを水洗いしてヒーターの上に干すのが日課でした。
右上の写真は、25年以上前に最初の英国で購入したゴルフ長靴です。2度目の英国の時は日本に忘れて使えなかった(金属スパイクなのでいずれにしても使えない)のですが、今思えば、このゴルフ長靴があれば重宝しただろうなぁ、と残念に思います。その代わりにブーツタイプのシューズを見つけて即購入。冬の間はずっと使用していました。(泥だらけであることには何ら変わりませんが)
このコースコンディションの季節差は、排水設備(構造)の有無によるのではないかと思っています。公営のコースではこの傾向が強く、初期投資を抑え、リーズナブルな料金にも繋がっていると思われます。初期投資の点からすると、地形差が大きいです。一般に日本は山岳コースが多くあり、その造成費は自然の地形を活用できる米・英と比べると高くなるのは当然です。更に、クラブハウスも日本のものは立派で、レストランやお風呂まであり、シャワーとパブの英国と比べると明らかに料金の差が出てしまうのは当然かと思います。
もう一つ、初期投資だけでなく維持費でも違いを感じたのは、細かいことですが、芝を刈った後の処理です。英国のコースでは、ラウンド後にシューズの裏に芝がびっしり付いていて、当初はグリーンリペアで芝を取っていました(後にエアで吹き飛ばす設備が入りました)が、まず日本ではシューズの裏に芝が付くということは殆どありません。何故だろうと思っていたら、ラフの芝刈りを見てわかりました。刈られた芝がそのまま放置されていたのです。足の裏にびっしり付く訳だと思いました。経費の削減なのでしょう。
◆プレースタイルについて
題名の「ゴルフバックを担いで」は、ゴルフのプレースタイルの違いから来ています。ゴルフコースの違いで述べましたように、英国では冬場はコースが柔らかく電動(もしくはガソリン)カート(以下、カート)は勿論、手引きのものでさえ禁止されますので、冬場のプレーはゴルフバッグを担ぐしかなくなります。その為、英国では最初から夏場でもゴルフバッグを担いでプレーをしました。夏場では一日2ラウンドすることも頻繁にあり、流石に2ラウンド担ぐのは疲れましたが、一度だけ一日で3ラウンド担いで回ったこともあり、良き思い出になっています。最近の英国では電動アシスト手引きカートがよく見られ、リモコン操作も可能で、プレイヤーに一緒にくっついて動く様子は、まるで忠犬を連れているようで微笑ましく思えました。
米国では、北部に住んでいたので雪で閉鎖される冬場の心配は不要で、夏場はレンタル手引きカートでプレーしていました。日本では、たくさんのお客様を効率よくラウンドして頂くにはカートを使用するプレーがMustになっていると思いますし、山岳コースが多いので、カートなくしてはプレー出来ない、次のホールにたどり着けないと思います。
もう一つの大きな違いは、コースのマネジメントです。日本ではたくさんのゴルファーにプレーして頂くためにインとアウト同時にスタートして、ハーフで食事を取って時間調整した後、残りのハーフをプレーすることになるので、1ラウンドをプレーするのに1日仕事になり、往復の交通渋滞も考えますと早朝から夜まで本当に1日潰します。が、米英では、18ホールを通してプレーするのが普通で、午前中又は午後に1ラウンドをプレーして、半日は家族サービスが出来ます。
私の限られた経験を通してですが日米英のゴルフ事情をご紹介しましたが、如何でしたか?
今後、海外でゴルフをする機会がございました時に、少しでもご参考になれば幸いです。
最後に、折角ですので、私のお気に入りのランチ〔冒頭の写真〕と是非とも紹介したいゴルフコースの写真も載せて、今回のコラムを終わりたいと存じます。

Walesの小さな半島にあるNefyn & District Golf Club です。
親しい仲間とのゴルフトリップで、大変人気のあるコースです。


狭い半島の尾根のフェアウェイに向かって、海越えで打っていきます。スリル満点です。
グリーンは遠くに見える灯台の麓です。(左)
その灯台の上にあるTee groundから打ち下ろすPar3のホールです。(右)
(K)

家庭用照明器具でも有名な企業

引用元)日経ビジネス6月21日掲載分
新型コロナウイルスは、感染力の強いデルタ型(インド型)が主流となり、“第5波”という形で猛威を振るっている。その中で急務になっているのが国民全般へのワクチン接種だ。今日はそのワクチン接種の現場で活躍している機器のお話。日経ビジネスの2021年6月21日掲載の記事を要約しながら紹介する。
記事では、
- 新型コロナワクチンの収束に向けて欠かせないのがワクチン接種。そしてワクチンによっては零下数十度という超低温での管理が必要。
- ワクチンを国内に普及させるためには低温で温度管理を安定的にできる超低温に維持する機能と全国津々浦々迄運搬できるコンパクト性を兼ね備えた特殊な冷凍庫が必要。
- 新潟市燕市のツインバード工業は、一般の人には用途すら思い浮かばないそんなマイナーな機器を迅速に増産している。
- ツインバード工業の製品でワクチンの運搬に使われているのが「ディープフリーザー」と名付けられた機器。 (ちなみに2021年4月迄に武田薬品工業と厚労省へ5000台ずつ納入された。)
- ツインバード工業は、実用化の目途も立たなければ将来の市場規模すらはっきりしない、多大な投資をしても結果が出るか否か不明な研究を続行して製品とした。
と、製品開発への取り組みを紹介している。
ツインバード工業の機器はどのようなものか。簡単に説明すると、
- この機器は、高さ46㎝の箱型で庫内は零下40度で冷やし続けることだけでなく、1度単位の温度管理が可能となっている。
- 重さは16.5kgと運搬もさほど難しくない。
- この冷凍庫の核となる技術はフリー・ピストン・スターリング・クーラー(FPSC)で、円筒内でピストンが往復運動をしてヘリウムガスを膨張・圧縮させることで冷却する。
という機能・性能を持っている製品だ。
記事では、資金の流れや資源についても指摘している。80年代以降、米国から日本の大企業に持ち込まれた株主至上主義により四半期決算が義務化されたことで、多くの大企業は株主の目を強く意識して短期収益主義に移行し、目先の利益の確保が優先されてマザー工場や基礎研究など事業の長期的持続に必要な部分には金を流さなくなった。そう考えると、もしFPSCの種を持つ大企業がツインバード工業以外にあったとしても研究対象にならなかった可能性が高いと分析している。そして、様々な製品で開発効率向上の名のもとに研究開発費も将来の事業化が見込める可能性の高いものに開発資源を集中するという事態となっている、と指摘している。
中小企業のほうが大企業よりも「株主至上主義」や「短期的利益」に捉われないで、独自技術を育んでいる会社がある可能性が高いかもしれない。しかし技術力に拠って立つ企業であるならば、中小企業だけでなく大企業でも他社が真似できない技術を持つことは大変重要だ。製造業など、技術力が必要な企業は、開発効率を重視して研究開発対象を短期の利益が見込めるものに集中するのではなく、以前の日本企業のように短期的利益だけでなく、長期を見据えた技術開発が必要ではないだろうか。
日本の製造業の技術力低下が言われて久しい。私自身は、まだそれほど日本の技術力が他国と比較して低下しているとは思っていない。しかし、だからこそ今、可能性が低いが将来の飯のタネになるような技術開発を大企業・中小企業ともに推進していくことが必要だと感じる。
(U)

脱炭素化の実現に向けて、グローバルで電動車化の動きが加速しています。米国での動きを今月6日の日経新聞では、以下のように伝えています。
===============
バイデン米大統領は5日、米国の新車販売に占める電気自動車(EV)など電動車の比率を2030年に50%に引き上げる大統領令に署名する。日本メーカーが得意とするハイブリッド車(HV)は含めない。 (中略) 米大統領が電動化の目標を示すのは今回が初めて。大統領令そのものに法的拘束力や罰則規定はないが、運輸省や米環境保護局(EPA)など関係当局に実現にむけた法整備や制度設計を命じる。
バイデン政権は30年に05年比で米国の温暖化ガス排出量を50~52%減らす脱炭素目標を打ち出しており、今回の大統領令はそれを進める柱のひとつとなる。20年の米国の新車販売は1446万台で中国に次ぐ第2位の規模。電動化が環境に与える影響は大きい。
(2021/08/06 日経速報ニュース)
===============
さて、電動車の比率を上げることは、車載電池の供給を増やすことが必要であり、それは長年注目を浴びている希少金属等の原材料の確保にますます注目が集まるということです。私自身、リチウムイオン電池の材料調達業務に長く携わってきた者として、材料サプライヤ共々、希少金属等の原材料の確保に苦労して来ましたが、今後急拡大が予想される電動車需要のもと、原材料の長期安定調達問題に直面されている方々は、今まさに大変なご苦労をされていると思います。
ここでは、安定調達にあたっての取り組みを、関連する記事から2点整理してみます。
最初に、原材料のひとつ、「リチウムの調達」です。
リチウムそのものは希少金属ではなく海水にも多く含まれており、理論上は海水からの抽出も可能ですが、今まではその採集が難しく、一般的には塩湖の水を蒸発で濃縮させたり鉱石を精製したりして、炭酸リチウムなどとして取り出してきています。しかし、塩湖の水を使う方法は生産に1年以上かかるほか不純物も多いという課題があると言われています。そこで、他の方法が検討されています。
===============
パナソニックは車載電池に使うレアメタル(希少金属)の安定調達を探る。このほど米石油サービス大手シュルンベルジェと提携し、地下水からリチウムを効率的に取り出す手法の検証を始めた。(中略)シュルンベルジェは塩水が含むリチウムを直接抽出することで生産期間を数週間に短縮できるという。(2021/07/17 日本経済新聞朝刊)
===============
リチウムの場合、生産期間短縮が従来から大きな課題であったので、この手法で生産期間が短縮できれば、安定調達に向けて大きな一歩になると期待されます。
ふたつめは「リサイクル」です。
===============
JX金属は電気自動車(EV)に使うリチウムイオン電池を回収する新会社を8月1日付でドイツに設立する。産出量が限られるリチウムやコバルト、ニッケルなどのレアメタルをリサイクルする試験装置を設ける。欧州自動車メーカーと連携し、2022年秋から稼働する。 (中略) 車載用電池のリサイクル需要が高まるのは30年以降とされるが、技術確立と調達網の整備で先行する狙いだ。(2021/07/22 日経産業新聞)
===============
先のリチウムのように新たな生産方式で生産量を増やす、あるいは、希少金属を使わない電池など新しい技術開発を実現することに加え、使用済みの電池から原材料を回収・再利用する技術開発や体制整備も欠かせないものとなってきています。
ところで、皆さんはオリンピックのメダルの材料もリサイクル品ということをご存じでしたか? 家庭から回収した小型家電や携帯電話の金属部品から出来ているのだそうです。
私自身、日常生活で分別回収されたものの行先を普段あまり意識していませんでしたが、あらためて、身の回りでのリサイクルの重要性を意識してみる機会になりました。
皆さんはいかがでしょうか。
(H)
ダンボールワンは6年で売上高10倍50億円を実現した北陸金沢に本社を置く会社です。特に先端素材を使ったり、先進機能があったりするわけではありません。お客様の商品に最適な段ボール箱を少量から送料無料の翌日配送で最大90%のオフプライスでWeb販売しています。社長の辻氏は元々は学生起業家で、北陸地方の産品をE Cサイトで販売していました。22歳でこの事業を売却し、当時の能登紙器に入社しました。大企業よりも町工場の方が成長できると考えたそうです。入社当初は学生起業で得たE Cサイトの知見を最大限活かして取り組みましたが、売上げは半年経っても1万円と低迷していました。発展の知恵は現場でお客様のニーズをもう一度当たることにありました。やはりお客様に聞けば、価格重視、納期重視であることが改めてわかったということです。ダンボール素材の在庫を覚悟して、自動見積もり・即日出荷体制・スマートフォンからの発注体制を整備した頃から売り上げが伸び始め、2年後には2500万円にまで成長しました。その間に社内の経費削減に向けて得意のデジタル化を一気に進めていったのはもちろんです。
ちょうどその頃、オーナーが会社売却を考えたことがきっかけでM B Oを実施し、辻氏が買い取りました。そして会社をプラットフォーマーに転換します。具体的には、ダンボール業界が地域の細かいニーズに密着した多品種対応の小企業の集まりで、年間の繁忙期閑散期の差が大きいことに着目。そして、全国のダンボール会社100社余りをつないで、閑散期を利用して生産し、全国のお客様に即納することで販売増を図ることに成功しました。これにより、今やダンボールワンの自社生産比率は3%にまで低下し、ダンボール製品のマーケティングと開発の会社となっています。今後はさらに売上げで6倍の300億円、市場シェア1%を目指すということです。

===============
◆小企業がデジタル化で成功するためのポイント
・Eコマースと社内手続きのデジタル化で経費削減をまず実施し原価低減を図る
・現場・お客様のニーズにもう一度真摯に向き合い、デジタル化での解を考える
・小企業同士をデジタルプラットフォームで繋ぎ、相互に資産活用を図る
小企業は自社のみでデジタル化を武器に成功することも考えられます。一方で産業自体が構造的な課題を持っている場合には、その課題をデジタル化で解決する方向が成功への道だと考えられます。つまり、同じような構造的課題を持つ小企業がタッグを組んで、持てる資産を相互活用することで強みに転換することが可能となります。
◆今後の展開
自社広告入りパッケージ(ダンボールワンの広告入り段ボール箱)、デザイン印刷、ラクスルからの資金と人材の導入での顧客拡大、これらにより一層の発展を考えているとのことです。
===============
ぜひ、自社の業態や製品・サービスに置き換えて考えてみていただければと思います。
(東出)

東京オリンピックが開幕しました。
良くも悪くも、という印象を漂わせながら。東京都に緊急事態宣言、そして周辺3県に“まん防”が適用されている中、とにかく始まりました。
代表の選手がその努力をいかんなく発揮すべく懸命に頑張っている姿がTVを通して伝えられています。この文章を書いている競技3日目の段階で既に日本のメダリストが続々誕生していることは快挙です。日本最年少13歳の金メダリストまで現れました。もちろんメダリストだけでなく、全ての選手はかつてない“見えない不安”に打ち勝ち、そして戦いの場に上がっています。これは選手の努力を大いに褒めてあげるべきです。
片や、社会の状況は新型コロナ感染防止策に対する効果が薄れつつあります。実際、その綻びがアチコチに見えるようにもなってきました。開会式からわずか3日ですが、やはり気になる動きがいくつもあります。そんな事柄からいくつか話題を拾ってみたいと思います。
■オリンピック関係者のクラスタ
オリンピックの開幕直前から選手や関係者に相次いで感染者が出てきました。この点は「開催する以上は必ず出るだろう」とは誰もが思っていたと思います。そんな中、五輪警備で全国から応援派遣されている警察官からクラスタが発生してしまいました。同じ宿泊先の50人が隔離されるという事態になっているそうです。感染者は同じフロアに滞在して同じトイレ・洗面所を使用していたということですが、これには「まるで過去の学習が活かされていない」という印象が強いですね。東京都交通局で発生した地下鉄大江戸線の運転士クラスタとよく似た話です。あの時は減便運転を暫く行なわざるを得なくなり、市民生活にも大きな影響が出ましたね。開会式関連でSNSにも画像が上がっていますが、今回のオリンピックの主要移動手段は「観光バス」です。既に運転手さんから感染者も出ているという話もあります。エッセンシャルワーカーとも少し違う立場ながら、オリンピックを支える側の感染防止策が徹底されているか速やかに再点検して、必要な対策を施す必要はありそうです。
■ワクチン配給の再開がいまだ見通せない
首長が口を揃えて「生命線」と語りながら7月初めに全国的に急ブレーキがかかったワクチン接種。オリンピック関係者への接種は優先的に進みました。しかし、一般市民向けの接種では未だ予約再開のメドが見えません。私の住む川崎市も、ご多聞に漏れず、病院での予約はもう3週間も停まっています。政府はこの事態が訪れることを5月にはわかっており、そして「隠していた」(という認識を病院・医療従事者が持っている)訳で、この点は実に罪深いです。基礎疾患のある重症化リスクの高い人の予約が長期で停まっていることを考えると、予約再開時には改めて「優先順位」を再定義する必要はあるでしょう。この対応は政府に限らず、国会/地方議員に対する評価に直結する政治行動になるでしょう。特に衆議院は秋に選挙を控えているので、「どれだけ行動できる人か」を実績で見せられないと、与野党に限らず“お役御免”という評価を頂くことになると思います。
■外出を促しているメディアの姿
もはや“不要不急”はどこ吹く風?という感じのメディアの動きには驚きました。表向きは「外出自粛を!」と呼びかけながら、いざオリンピックが始まれば、オリンピック公式グッズショップに集まっている買い物客に話を聞きに行き、そして、“盛り上がり”を伝えて購買意欲を高める報道をしています。「不要不急の外出は控えましょう」と呼びかける側のメディアが既に“諦めている”感じです。
しかし、これは「何が正しいかがわからない」ことの裏返しでもありますね。
メディアのほとんどが民間ビジネスであり、彼らも生活をなんとか作っていかなければならない中で、皆さんが関心を持つことを提供する本分を全うしようとすると、どこかで“矛盾”も腹落ちさせないといけません。「みんなが集まらずに、多くの人が関心を持つもの」を探し続けるという挑戦を続けなくてはならないというのも、このコロナ禍がメディアに突き付けた「今後の仕事や生活に向けた大きな課題」であることも間違いないと思います。
コロナ禍への対応がまとまりをなくしつつあり、またコントロールする方法も既存システムでは限界があるようです。今回のオリンピックでは「エリア分けによる感染防止策」ということで、欧米で言うところの「バブル方式」を採用していますが、正直なところ、既に綻び弾けている印象が残ります。「バブル」と聞くとあまり良い想い出のない世代の私ですが、このオリンピックでもまたそんな印象が残ってしまいそうです。
今回は経済面の見立てについては触れませんでしたが、オリンピック・パラリンピック後の世界経済に思うことは機会を改めてお話ししたいと思います。一層高まるであろう“摩擦”にどう対応するか考えていきたいと思います。
(鯨井)
今週は東京オリンピックが開幕しますね。コロナ禍での開催ということもあり、様々な意見が交錯していますが、せっかくなので今回はスポーツの話題にしたいと思います。
私は、仕事の関係で米国、英国、英国と海外で生活する機会が3度ありました。現在は60歳代半ばですが、家族帯同で赴任したのは米国での30歳代前半と1回目の英国での30歳代後半でした。2回目の英国は単身、60歳を迎えてからでした。私は、アパートの前がゴルフ練習場だったことがキッカケで20代後半にゴルフを始めました。日本では50歳過ぎにゴルフコースのメンバーになり、年間20~30ラウンドの平均スコアが90台前半のアベレージゴルファーで、所謂、競技志向のアスリートゴルファーではありません。目指そうとしてメンバーになりましたが、才能とお金がないので諦めたというのが実態ですが。オリンピック・パラリンピックの期間に来る私のコラム担当回で、日米英でのゴルフ事情についてご紹介します。今回は料金と予約/キャンセルについて、次回はコースとプレースタイルについてお話しします。少しでも関心を持って頂けましたら幸いです。また、時間(時代)差も含んだ個人的な感想の紹介ですので、一般論ではないということは最初にご理解頂きたいと存じます。


【写真について】
1枚目は2019年のAIG全英女子オープンのチャンピオンになった渋野プロとの写真です。最終日の朝の練習が終わり、パターの練習に行く前でした。これから最終組で優勝争いをする時なので遠慮がちにお願いしましたが、渋野プロは気持ちよく撮影に応じて下さり、女子・男子通して初めてのプロゴルファーとの写真が、渋野プロであったことに本当に今でも驚いています。その後、18ホールを応援して回り、あの劇的な優勝シーンに立ち会えたのは本当にゴルファーとして、とてもラッキーでした。勿論、その後はいつも渋野プロを応援しています。オリンピック候補から外れたのは大変残念ですが、これからも海外にチャレンジして欲しいです。
2枚目は、英国での私のメンバーコースの名物ホール、キャリーで160-190ヤード必要な池越えPar3。Private Courseで2つのチャンピオンコースがあり、週末はゲストは£60くらいでプレーできました。今、ネットでみると£80です。年会費も上がっているのかなぁ?
■ ゴルフ料金(プレーフィー)について
一般的に、日本が高く、米国と英国はほぼ同じイメージですが、為替レートで円換算すると、日本≫英国>米国のイメージです。どの国でも、どのコースでプレーするか、会員になるか、年に何ラウンドするか等によって異なっています。更に、英国は午後のオフピークになると午前の半額(£25)くらいになり、空いているので気楽にプレーが出来ました。
英国(多分、米国も?)では、年会費で会員になり、年会費だけでプレーし放題です。私の場合、2年前で約£2,000でしたので、¥150/£換算して年間約30万円で、プレーし放題、コース横のプールやジムも使い放題でした。練習場も約半額で練習でき、ショートコース(もちろん無料)やアプローチグリーンもあり、ゴルフの環境は抜群でした。Golfaholic(ゴルフ狂)には最高の環境だと思います。
日本だと、会員権を買い、年会費も払い、且つプレー料金も毎回かかります。私だと、神奈川県の会員コース(安いコースです)で年40ラウンドで年会費込みで36万円位かかり、金額はあまり変わりませんでしたが、英国では、週末だけでなく、夏は勤務後もプレーできますので、年間で60~70ラウンドは難しくありません。そうなると、ずっとお得感が出てきます。日本でも平日なら安くプレー出来るところもあると聞いていますので、その地元に住めば、かなり良いゴルフ環境が得られるのではないかと羨ましく思います。
■ ゴルフの予約/キャンセルについて
最近はネット予約が主流になっていますが、最初の米国、英国では電話で予約やキャンセルをしていました。当時25~30年近く前になりますが、米国では既にクレジットカードで予約をギャランティしていて、ドタキャンではフルでカードにチャージされて、契約社会だなぁと思った記憶があります。そのつもりで、1回目の英国での赴任時に、予約のドタキャンの電話をした際、❝Thank you for your call❞と言われ、キャンセル代も請求されずにお礼まで言われて、以前の米国と比較して感激したことと、社会的な豊かさを感じたことを覚えています。2回目の英国では、早々に会員になり、またドタキャンもしなかったので、実際のところどうなっていたのかわかりません。私の今のコースでは、キャンセル料金は一人当たり1500円です。
次回は、ゴルフコースとゴルフのプレースタイルについてお話しします。
なぜ日本のゴルフ料金は高いのか、そのコースを考えると「なるほど!」と言える事情もあります。
楽しみにしていて下さい。
(K)

現在、スマホユーザーはアプリを平均103個ダウンロードして使っています。このうち38.5個を実際に利用しているそうです。(モバイルマーケット白書2020による。)
PCで利用するWebサービスを含めれば、私たちが管理するパスワードは膨大な数になります。
■個人のパスワードの運用、管理の実態は
トレンドマイクロ社の2020年の調べによれば、85.7%の方がパスワードを使い回していることが判っています。ちなみに、全てのWebサービスで異なるパスワードを設定している方は、全体のわずか14.4%です。パスワードを使いまわす理由は、「異なるパスワードを設定すると忘れてしまう」が71.4%と最も多く、「異なるパスワードを考えるのが面倒」が49.4%と続きます。パスワード設定の手間がユーザーを悩ませていると推察できます。
それでは、パスワードの設定の仕方、運用と管理はどのようにしたら良いのでしょうか?
総務省のHPにある設定・運用・管理の記事を参考に、解説を加えていきたいと思います。
■パスワードの設定の仕方
「安全なパスワード」と「危険なパスワード」をそれぞれ以下のように定義しています。
「安全なパスワード」とは、他人に推測されにくく、ツールなど(例えば総当たり攻撃、辞書攻撃…)で割り出しにくいものを言い、
(1) 名前などの個人情報からは推測できないこと
(2) 英単語などをそのまま使用していないこと (英単語の一部を意図的に間違えるなども有効)
(3) アルファベットと数字が混在していること (複数の文字種を利用すること)
(4) 適切な長さの文字列であること
(5) 類推しやすい並び方やその安易な組合せにしないこと
としています。
逆に、「危険なパスワード」としては、以下を挙げています。
(1) 自分や家族の名前、ペットの名前、生年月日、住所、車のナンバーなど
(2) 辞書に載っているような一般的な英単語
(3) 同じ文字の繰り返しやわかりやすい並びの文字列
(4) 短すぎる文字列
つまり、「ある程度の長さの文字列で、複数の文字種を使ったパスワード」が安全であるということです。
■推奨されるパスワードの運用と管理
パスワードは、複数のサービスで使いまわさないことが重要です。(但し、定期的な変更は不要。) あるサービスから流出したアカウント情報を使って、他のサービスへの不正ログインを試す攻撃の手口が知られています。もし重要情報を利用しているサービスで、他のサービスからの使い回しのパスワードを利用していた場合、他のサービスから何らかの原因でパスワードが漏洩してしまえば、第三者に重要情報にアクセスされてしまう可能性があります。
従来は、パスワードは一定期間(例えば3ヶ月など)を過ぎたら変更することが推奨されていましたが、最近は「パスワードの定期的な変更は不要」とされています。それよりはパスワード設定のガイドラインに沿って他人に推測されにくいパスワードを設定し、かつ各Webやアプリ毎に異なったパスワードを設定することが求められています。
■パスワードのリスクマネジメント
改めて、パスワードを使いまわす原因について考えてみます。
前述の通り、パスワードを使いまわす理由が「各々のWebやアプリ毎にパスワードを設定すると忘れてしまう」「考えるのが面倒」というコメントにあるように、個人で40~50個あまりのパスワードを管理するのは困難です。その結果、簡単なパスワードを設定してしまい、パスワードの漏洩へ繋がり、パスワードを使い回していると重要な個人情報の漏洩へと繋がります。
しかし、パスワードを使い回さないためには、管理しなければならないパスワードの数が膨大になってしまい、結局簡単なパスワードの設定に繋がってしまいます。
ここで興味深いコメントがあります。
パスワードを1箇所に書き留めることは、パスワード管理において長年タブーとされてきましたが、Google社のアカウントセキュリティ担当者であるマークリッシャー氏は、パスワードを書き留めることを推奨しています。(So-netセキュリティ通信 2021年3月23日より引用)
例えば、パスワードをエクセルシートに書き留めた場合、エクセルシートにアクセスされるリスクもありますが、複数のサービスで使いまわしているパスワードを第三者に悪用されるリスクの方がはるかに高いと指摘しています。
普段利用するWebサービスやアプリの数が増えた場合、それらのサービスやアプリ毎にパスワードを設定する必要が生じ、それらを管理しなくてはなりません。その際に一つ一つパスワードを変えて設定しなくてはならず、簡単なパスワードを設定するという結果に繋がっているならば、桁を増やすなどパスワードを複雑にしてセキュリティーの強度を上げ、パスワードの管理はメモに残すようにする、ということです。
私の経験上、このようなパスワードの設定・運用・管理で、“突破されにくいパスワード”を設定し、複雑なパスワードを忘れないようにメモなどで残して、そのメモはきちんと管理(紙で保管する際には“鍵付きの場所”に保管)するのが合理的だと思えます。
さて、皆さんはどう思われたでしょうか。
(U)

私が担当したコラム「新車販売、5ヵ月連続プラス、2月、半導体不足など懸念」(#023)で、コロナ禍で販売が落ち込んでいた自動車販売の回復について触れましたが、今回は自動車部品業界について触れてみたいと思います。
自動車部品業界も全体としては回復の兆しが出てきています。しかし、脱炭素化、CASE他昨今言われている市場環境や技術の変化による個々の企業に対する影響が、目に見えるような形で現れてきています。そこには明も有れば、暗もあります。
最近の日経新聞他では、以下のように伝えています。(引用)
===============
日本自動車部品工業会(部工会)はこのほど自動車部品メーカーの経営動向調査を公表した。主要46社の2021年度の合計純利益は前年度比63%増の8825億円を見込む。半導体不足の影響はあるが新型コロナウイルス禍からの回復傾向が続く見通しだ。ただ中長期的には脱炭素対応への負担が自動車部品メーカーにも重くのしかかる。
(中略)
内燃機関を搭載した車はいまだ多く存在することから部品メーカーには引き続き供給責任はあると話す一方、電動化に向けて事業ポートフォリオを変えていく必要性にも言及した。両立は難しいものの「経営者は思い切って舵を取らないといけない」と指摘した。
===============
ここでは、自動車部品業界全体として、回復傾向にあるものの、企業の存続にあたっては、事業ポートフォリオの変更の必要性が言及されています。関連する話題をキーワードと共にいくつか紹介したいと思います。
まずは、「将来へ向けた新たな取り組み」です。
1)キーワード:<脱炭素化>
神戸製鋼所はEV用モーターを2割軽くできる鋼材を開発。「アキシャル型」と呼ぶモーターの中核部材に使う鋼材。4月に事業化に向けた専門組織「磁性材マーケティング開発室」を立ち上げ、まず自動車会社へのサンプル出荷をめざす。
(神鋼、EVモーター軽量化、新鋼材開発で2割軽く航続距離の延長を後押し。2021/7/1 日本経済新聞)
2)キーワード:<空飛ぶクルマ>
デンソーは、搭載するモーターの重量を3分の1にするめどをつけ、2022年中に部品を搭載した機体での試験飛行を予定。自動車部品に次ぐ新たな経営の柱にすることをめざしている。
(「空飛ぶクルマ」軽量化にめど、デンソー、新モーター開発へ。2021/6/24 日経産業新聞)
3)キーワード:<衝突被害軽減ブレーキの装着義務付け>
日本セラミックは国土交通省が2021年11月から段階的に衝突被害軽減ブレーキの装着義務付けを決めたことを受けて、自動ブレーキ向けセンサーを増産。21年12月期から5年間で約20億円を投じて自動ブレーキ関連の生産設備を増強して生産能力を高める。
(車自動ブレーキ用センサー増産、日本セラミック、5年20億円投資。2021/7/2 日経産業新聞)
等、自動車の将来へ向け、部品メーカー、素材メーカーを問わず、いろいろな新たな取り組みを拡大しようとしています。
次に、「厳しい」話題です。
4)キーワード:<脱炭素化>
●ホンダが栃木県真岡市にある四輪車向けエンジン部品工場を2025年に閉鎖する。ホンダは40年に世界で販売するすべての新車を排出ガスがない電気自動車(EV)など「ゼロエミッション車」にする目標を掲げており、調達構造がまったく変わる。
(ホンダ、栃木部品工場25年閉鎖、真岡市、下請けへの支援検討。2021/7/1 日経産業新聞)
●自動車エンジン向けにアルミニウム鋳造設備を開発・製造していた大阪技研(大阪府松原市)の破産手続き、4月に開始決定。ホンダの電気自動車(EV)シフトが影響。
(参考:急激なEVシフト受け破産、大阪技研、エンジン開発中止で。2021/6/29 日経産業新聞)
このように、自動車部品業界は、明暗それぞれに大きな変化が起き始めています。
では、この変化に向けて何をしていかなければならないのでしょうか。
最も大切かつ難しいのが、従来の自動車領域を超えた世の中の変化の先読みでしょう。
上記の話題で言えば、
・脱炭素化の世界レベルでの急速な動き
・安全装備等の法規制化の動き
・既存の形態を超えた商品の変化(車は地上を走るもの→飛ぶもの)
です。少し前まで、このようなことが想像できたでしょうか。想像できたとしても、事業をそこへ向けて変化させることが出来るでしょうか。
変化の激しいこの時期に、
① 自社の強み弱みの把握
② 新しい動きをつかむ情報収集、分析
③ それらを基にした事業ポートフォリオのチェック、見直し
を常に意識しておくことが必要でしょう。
みなさんは、いかがでしょう。
(H)
お気軽にお問合せください

お問合せやご相談のご予約
ビジネス未来&Co.では、事業開発やビジネスコンサルティング等に関するお問合せや相談予約を専用フォームで受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。
を開設
(2025年4月活動分より)